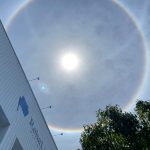2023/07/19

リハライフプラス所長の頼田です。
今回のタイトル、ちょっと大げさに聞こえるかもしれません。
しかし、日々デイサービスを運営する中で、この言葉の意味を痛感するようになりました。
もともとうすうす感じていたことではありますが、現場で利用者さんと関わり、スタッフと話し合い、地域の方と向き合うなかで、
「一次情報こそが、意思決定の軸になる」
そう実感する場面が増えています。
そこで今回は、
「一次情報が、デイサービス運営にどう影響するのか」
を、実際の体験談を交えながら深掘りしていきます。
サクッと読めて、かつ何かヒントになるような内容になっていると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。
目次
一次情報ってなに?

まずは、「一次情報ってなんだ?」ってところから。
かんたんに言うと、
自分(わたし)が実際に見たり、聞いたり、感じたりした“生の情報”
のことです。
たとえばリハライフプラスの現場なら──
- 利用者さんがふとこぼした一言
- リハビリや歩行中の反応
- ご家族のちょっとした表情やトーン
- スタッフとの会話での気づき
こうした自分が直接見たり、聞いたものが「一次情報」です。
逆に、
- 「○○さんがこう言ってたらしい」
- 「ネットやテレビで見た情報」
- 「ケアマネさんがこう言っていた」
- 「家族さんが話していた」
のように、誰かを通して伝わってきた情報は二次情報・三次情報と呼ばれます。
一次情報がなぜ大事なのか?

結論、
「判断と行動の精度が上がる」からです。
責任者をやっていると、日々さまざまな事案に対して「判断したり、行動したり」する必要があります。
その判断の精度が高ければ高いほど、
- トラブルが未然に防げる
- 利用者さんやスタッフからの信頼が高まる
- 店舗の数字にも直結する
つまり、
「判断・行動の質=会社の明るい未来」
と言っても過言ではありません。
二次情報や三次情報にはどうしても「フィルター」がかかります。
話を伝える人の主観や解釈が混ざるので、元のニュアンスが変わってしまうことがあるんです。
もちろん、二次情報や三次情報も参考になります。
しかし、人から聞いた話を鵜呑みにして動いた結果、思わぬ展開になったということも多くありました。
Before → Afterの例

① ケアマネさんからの紹介ケース
Before(二次情報)
↓
After(一次情報)
➡ 二次情報のイメージで判断していたら、機会損失になっていたかもしれない。
② 他店舗のフォロー要請ケース
Before(二次情報)
↓
After(一次情報)
➡ 部分的なサポートが正解だったケース。
③ 記録だけを見て判断したケース
Before(二次情報)
↓
After(一次情報)
④ 業務効率化のケース
Before(二次情報)
↓
After(一次情報)
➡ 現場で流れを見たからこそ改善策が出せたケース。
⑤ 「みんなが言ってる」と聞いたケース
Before(二次情報)
↓
After(一次情報)
➡ 「みんなが言ってる」は、主観の混じった二次情報であることが多い。直接ヒアリングして確かめることの重要性を再確認した。
⑥利用者さんの声を直接聞いたケース
Before(二次情報)
↓
After(一次情報)
➡ 本人の希望を把握し、サービス内容を調整することで継続利用につながった。
どうでしょうか?
けっこうあるあるな内容なのではないでしょうか。
この「Before(二次情報)→After(一次情報)」の違いがあるだけで、判断の軸が大きく変わります。
一次情報を取りにいくことは、未来のトラブルを防ぎ、チームの安心感を生む一番の近道なんじゃないかなと思います。
行動のポイントと、最後に伝えたいこと

何事もやってみないとわからない。
現場に足を運び、チャレンジして自分で体験してみることで、
今まで気づかなかった課題や改善のヒントが見つかります。
この“自分で感じた気づき”が、次の判断や行動の精度を上げてくれます。
一次情報の質を上げるミニチェックリスト
- 必ず一度は現場を自分の目で見る
- 記録や伝聞は“仮説”として扱い、現場で検証する
- 不安や疑問は一次情報を取りに行って解消する
- 観察→判断→結果→振り返りをチームで共有する
送迎中の渋滞も、
人から「渋滞多いよ」と言われているうちはピンとこないですが、
自分が実際にハマって焦って痛い目を見て初めて「これは気をつけよう、コースを変更しよう」となる。
責任者である自分が、
- 現場で何を感じるか
- どう判断するか
それが店舗のこれからの世界をつくっていくんだと思います。
もちろん、ピントがずれた判断をしてしまうこともあります。
その結果、チーム全体のパフォーマンスに影響することもあるでしょう。
でも、
一次情報を得る → 判断する → 結果を検証する → 修正する
この繰り返しで、少しずつピントは合っていきます。
そしてピントが合ってくると、判断の精度が上がり、スタッフや利用者さんの安心感も増していきます。
一次情報は、ちょっと手間がかかります。
でも、その一手間が未来のトラブルを防ぎ、チームの信頼をつくる大きな力になる。
今日の現場でも、
「自分の目で確かめる」
この意識を持ってみてください。
きっと見える世界が変わるはずです。
以上です!
ありがとうございました!