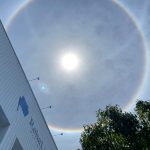2023/07/19

リハライフ卸団地二階所長の弘田です。
日本一早く咲いた高知の桜も葉桜となり、その代わりにツツジの花が咲き季節が進む早さに驚く日々です。
今回は「栄養」についてお話したいと思います。
皆さんはご自身の栄養状態について考えた事がありますか?また、それがリハビリにどう影響するのでしょうか?
最近食欲が無くなってきたり、食べやすい食品(柔らかい食品)ばかり食べているなど思い当たる節はありませんか?
低栄養の状態で運動を行った場合、足らない栄養を体はどう補っているのでしょう?
答えは、筋肉を分解してエネルギーとしています。ということは、運動が過負荷であった場合どんどん痩せていってしまいます。
足の筋力をつけたいと頑張って運動をしていたのに、食事が不十分だったために思うような効果がでない方は栄養に着目してみてはどうでしょうか?私達も日々利用者様とリハビリをしていく中で、食生活について質問させて頂くことがありますがそれにはこの様な理由があったからです。
では、ご自身の栄養状態をどのように評価すればいいかご説明します。まず体重やBMI(体重を身長の2乗で割った値)が挙げられます。また、体重は現在の値が多いか少ないかのみではなく過去数カ月の間で増減したのかにも注意する必要があります。リハライフでは毎月体重測定を行っておりますので、過去の値が気になる方はスタッフまでお尋ねください。
また、近年高齢者を対象とした栄養スクリーニング、アセスメントとしてMNA(簡易栄養状態評価表)があります。これは、専門的な知識が無くても評価が可能なので、おすすめします!興味がある方は是非検索してみてください。
高齢者の方が食べられなくなるには、様々要因が挙げられます。
①全身状態の悪化や基礎疾患
発熱や脱水があった場合、全身倦怠感により食欲が低下します。また心不全は、全身性の炎症反応を伴うため、長期間の食欲低下と体重の減少から低栄養が進行していきます。
②嚥下障害
脳梗塞などの脳血管障害や、パーキンソン病などの神経変性疾患が原因で嚥下機能の低下をきたし、食事摂取量が減少する方が多くおられます。
③口腔内のトラブル
高齢者の方では、残存歯が減少したり、咀嚼機能が低下したり、舌の機能が低下したりすることにより食事摂取に問題をきたすこともあります。また、口腔ケアの不徹底や義歯の不適合といったことも食欲低下、食事摂取量減少の原因となります。
④認知症
近年食事をとれない原因として急増しているのが認知症です。摂食障害が認められる認知症高齢者では、生存率の低下が顕著です。食べることは生命と密接に関わる重要な問題です。
以上のような事から、栄養がいかに大切かが改めて考えさせられます。
皆様も日々の食事について見直してみてはいかがでしょうか?