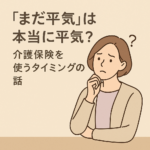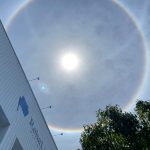2023/07/19

こんにちは
高須店の西川です
『ハンチバック』市川沙央著
今回は、この本を紹介していきたいと思います。
【Amazon 本の概要 より抜粋】
第169回芥川賞受賞。
選考会沸騰の大問題作!
「本を読むたび背骨は曲がり肺を潰し喉に孔を穿ち歩いては頭をぶつけ、私の身体は生きるために壊れてきた。」
井沢釈華の背骨は、右肺を押し潰すかたちで極度に湾曲している。
両親が遺したグループホームの十畳の自室から釈華は、あらゆる言葉を送りだす――。
この小説は、先天性ミオパチーの作者によって書かれています。小説の主人公もまた、作者と同様の身体障害をもっていると思われます。
障害を主とした作者の身体的特性と、小説の内容、そして芥川賞受賞会見での発言と、2023年当時に大きな話題になったことを覚えています。
◯ハンチバック:せむし。主人公が自らの背骨の湾曲を、ハンチバックの怪物と称しています。
作者の身体的特性や背景を前提として読み始めて、まず驚かされます。前提をひっくり返されます。その後も、小説の構造から、文体、社会批評、ユーモアまで驚かされることばかりのジェットコースター小説です。文章コントロールが行き届いているので、情報量の多さもするする入ってきます。短編ということもあり、読みやすさも抜群です。
最高の小説です。
この小説のテーマは、社会(世界)と自分の身体(精神を含む)についての作品なので、介護に重点が置かれているわけではありません。
しかし、舞台はグループホームであり、登場人物にヘルパーも出てくるため、我々デイサービス職員は我が身を振り返らざるをえません。
中に、こんな場面があります。
主人公が、ヘルパーに入浴介助をしてもらう時、主人公の心の声で「生殺与奪の権を握ったから気が大きくなっているのか?」と思うシーンです。
大事な場面なので、小説の内容は言えませんが、はっと思うことがありました。
デイサービスの利用者さんは、身体的な問題を抱えている方が多くいます。
対して、職員は気力体力ともに健康である方が多いです。
生殺与奪の権とまでは言いませんが、身体的な非対称性があることは間違いありません。だからこそ、介護が出来ているわけでもあります。しかし、そのことが不安を与えてしまう原因でもあります。
もちろん、我々職員は、利用者の皆さんに不安を与えないように色々と工夫をしています。
目線を合わせる、笑顔を絶やさない、優しく声をかける等、とても単純ですが、そういうことです。
もう少し詳しく、我々デイサービス職員の工夫について話します。
具体的な方法論としては、例えば、イヴ・ジネスト、ロゼット・マレスコッティの提唱する「ユマニチュード」という技術があります。この技術では、①見る②話す③触れる④立つ、という4つの順序をもって、声掛けの種類・身体接触の順番など、細かい方法論があります(『「ユマニチュード」という革命 なぜ、このケアで認知症高齢者と心が通うのか』著者イヴ・ジネスト、ロゼット・マレスコッティ、本田美和子)。
また、抽象的な倫理としては、利用者さんを理解しようと努めています。エーリッヒ・フロムのいうところ、愛は技術であり、知力と努力が必要なことです(『愛するということ』著者 エーリッヒ・フロム、訳者 鈴木晶)。利用者さんとできるだけコミュニケーションをとり、好みを知り、嫌いなものを知り、その人が大事にしているものを理解しようと努めています。
ケアを突き詰めると、「ここにいてもいい」ということを伝えることです。存在の肯定です。その為に愛があります。具体的には、呼べば応え、伸ばされた手を握ることです。
そうして一生懸命に考え、努力しています。
しかし、それでも伝わらないことがあります。
そのことが、ハンチバックの主人公の心の声に繋がります。
職員と利用者さんに、身体的な非対称性があることを思い出すことが出来ました。
職員に色々な考えがあるように、利用者さんにも色々な考えがあります。そのことを今一度、思い出すことが出来ました。
ハンチバックという小説は、固定概念や価値観を揺さぶってくる物語です。
読んだ後では、世界が違って見えるという、例のアレです。
つまり、最高の小説ということです。
介護の現場では、理想と現実の背骨が曲がってしまっていることがあります。ぎしぎしと音を立てて、肺を押し潰しながら、それでも踏んばっています。もがいています。
明日からも、どうか幸せな物語が溢れますように。